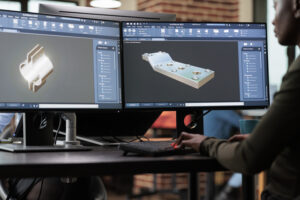ねじの基礎知識
このページでは「ねじ」についてご説明します。
- 目次
- ねじの概要
- ねじの種類
- ボルト
- タッピングねじ
- セットねじ(止めねじ・イモねじ・ムシねじ)
- 木ねじ
- 小ねじ
- ねじに関連するJIS
- まとめ
ねじの概要
ねじは、機械部品同士を固定するための締結部品で、古くから使用されている基本的な機械要素です。棒状のシャフトにらせん状の溝(ねじ山)が刻まれた構造を持ち、回転運動を直線運動に変換するメカニズムとしても機能します。ねじの特徴は、部品の締結・分解が容易で、再利用可能な点です。そのため、製品や機械の組み立て、メンテナンスに欠かせない要素です。
ねじは部品の固定だけでなく、ジャッキやリードスクリューのように、物体を持ち上げたり精密な位置制御を行ったりするためにも利用されます。このように、ねじは機械設計における多様な用途と重要な機能を持っています。
ねじの種類
ねじには様々な種類があり、それぞれの用途や機能に応じて使い分けられます。以下に、代表的なねじの種類とその用途を詳しく説明します。
1.ボルト
ボルトは、ナットと組み合わせて部品を固定するねじで、大きな締結力を必要とする場面で広く使用されます。建設機械や車両、構造物などの重厚な部品の結合に適しています。ボルトの種類には、六角ボルトや六角穴付きボルトなどがあります。
- 六角ボルト:六角形の頭部を持ち、工具で回して締め付けます。多くの産業分野で最も一般的に使用されるボルトで、頭部が大きいため締結力が高いです。
- 六角穴付きボルト:ボルトの頭部に六角形の穴があり、六角レンチで締め付けることができるタイプです。頭部が平らで目立たないため、限られたスペースや仕上がりを重視する機械の内部に使用されることが多いです。また、六角穴付きボルトは、ボルト軸に対して強いトルクをかけられるので、高い締結力が求められる精密機械でも利用されます。
2.タッピングねじ
タッピングねじは、あらかじめ開けた下穴に直接ねじ込んで固定するねじです。金属、プラスチック、木材に適した種類があり、ねじ山の形状や材質が用途によって異なります。タッピングねじは、素材を切削しながらねじ込まれるため、ねじ山がしっかりと形成されて安定した締結が可能です。電子機器の筐体や金属板の組み立てでよく使用されます。

3.セットねじ(止めねじ・イモねじ・ムシねじ)
セットねじは、部品の位置を固定するためのねじで、通常は頭部がないか非常に小さい設計です。軸や部品が移動するのを防ぐ役割を持ち、機械内部のシャフトに取り付けるギアやプーリーの固定に使用されます。狭いスペースで突出しないようにする設計が求められる場合に適しています。また、六角穴付きのセットねじも多く、高い締結力をかけることができます。

4.木ねじ
木ねじは、木材への締結に特化したねじで、ねじ山が深く設計されています。木材にしっかり食い込むように作られており、先端が尖っているため、あらかじめ下穴を開けずに取り付けることが可能です。家具の組み立てや建築用木材の固定に使用されます。木ねじには鉄製やステンレス製のものが一般的で、錆びにくいメッキ処理が施されていることもあります。

5.小ねじ
小ねじは、電子機器や精密機械の部品の固定に使用される比較的小型のねじです。通常、ナットと組み合わせて使用されることが多く、ねじ頭の形状には平頭、皿頭、トラス頭などがあります。
- ナベ小ねじ:頭部が丸みを帯びたドーム状になっており、見た目がなべの形に似ているため「なべ小ねじ」と呼ばれます。この形状により、平らな表面への座りが良く、比較的広い接触面積が得られます。
- 皿頭小ねじ:ねじの頭部が平面よりも下に沈むように取り付けられるため、仕上がりを重視したい場面で使用されます。
ねじに関するJIS規格
日本工業規格(JIS)は、ねじに関する規格を細かく定めており、ねじの形状、寸法、材質、強度、性能などが統一されています。これにより、異なるメーカー間でも互換性があり、製造や使用時のトラブルを防ぐことができます。以下に代表的なJIS規格を紹介します。
- JIS B 0205(メートル並目ねじ)
最も一般的なメートル並目ねじの規格です。ねじ山の形状やピッチ(ねじ山とねじ山の間隔)、径が規定されています。この規格に従うことで、国内外の異なるメーカーでも同じ基準のねじを製造・使用できるため、標準的なねじとして広く利用されています。 - JIS B 1111(六角ボルト)
六角ボルトの寸法、形状、材質、強度に関する規格です。六角ボルトは建築や機械、車両の部品固定など、さまざまな分野で広く使用されるため、JIS規格に基づくことで品質の確保と交換性の向上が図られます。また、耐食性を高めるための表面処理(メッキなど)も規定されています。 - JIS B 1176(六角穴付きボルト)
六角穴付きボルトの形状や寸法、材質、強度に関する規格です。六角レンチを使用して締め付けるため、狭いスペースでも作業がしやすく、外観がすっきりする特徴があります。この規格に従うことで、精密機械や自動車の内部部品など、高精度を求められる場面でも安定した締結が可能です。 - JIS B 1188(タッピングねじ)
タッピングねじの規格で、ねじ山の形状や先端の鋭さ、材質が定められています。これにより、適切な下穴の径や締結に必要なトルクが明確化され、効率的で正確な作業が可能です。電子機器の筐体固定や金属板の組み立てでよく使用されます。 - JIS B 1251(木ねじ)
木ねじに関する規格で、ねじ山の深さや先端形状、材質が規定されています。木材への締結力や耐久性が確保されており、建築用部材や家具の製作などで安全かつ高品質な作業が可能です。
JIS規格に従って設計・製造されたねじを使用することで、製品の品質が保証され、互換性が確保されます。これにより、ねじの選定や使用時のトラブルが防げるため、機械設計においてJIS規格の理解は非常に重要です。
まとめ
ねじは、私たちの日常生活から産業の最先端に至るまで、さまざまな場面で不可欠な役割を果たしています。小さな部品でありながら、高度な力学や材料の知識が求められる技術の結晶です。その精密な設計と正確な構造は、製品の安全性と信頼性を支える基盤となっています。ねじの仕組みを理解することは、ものづくりの本質に触れることであり、その奥深さは学ぶ価値が十分にありますね。ねじがなければ成立しない現代社会を支える要の技術を、ぜひ深く学んでみたいです!
なお、八田機械では特注ねじ(M1~)の製作も請け負っております。ねじの製造でお困りの方は、是非八田機械にご相談ください。